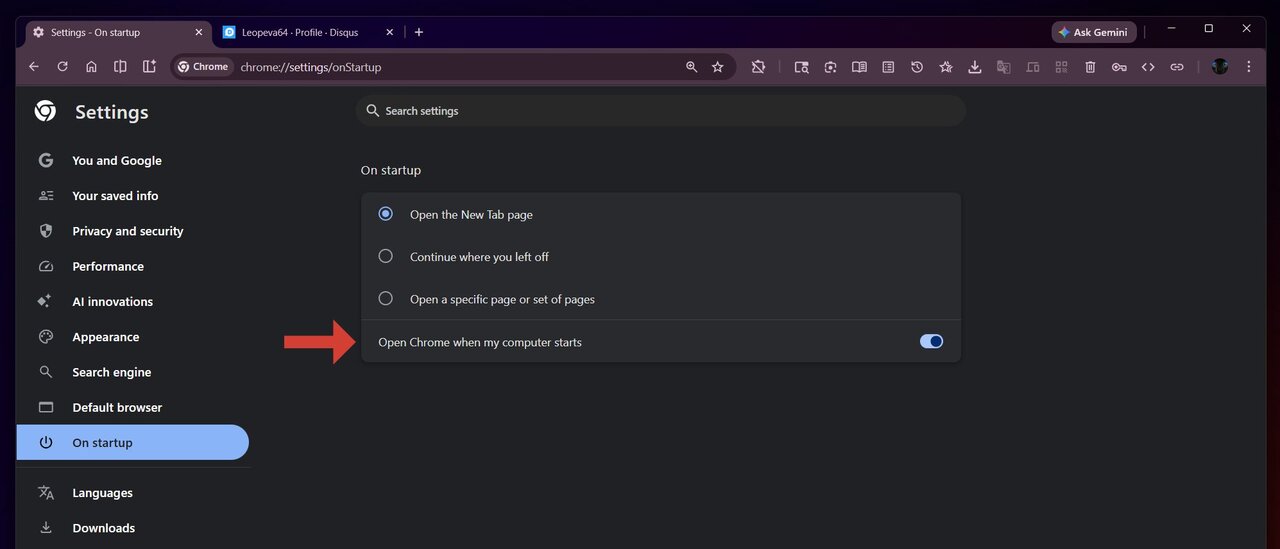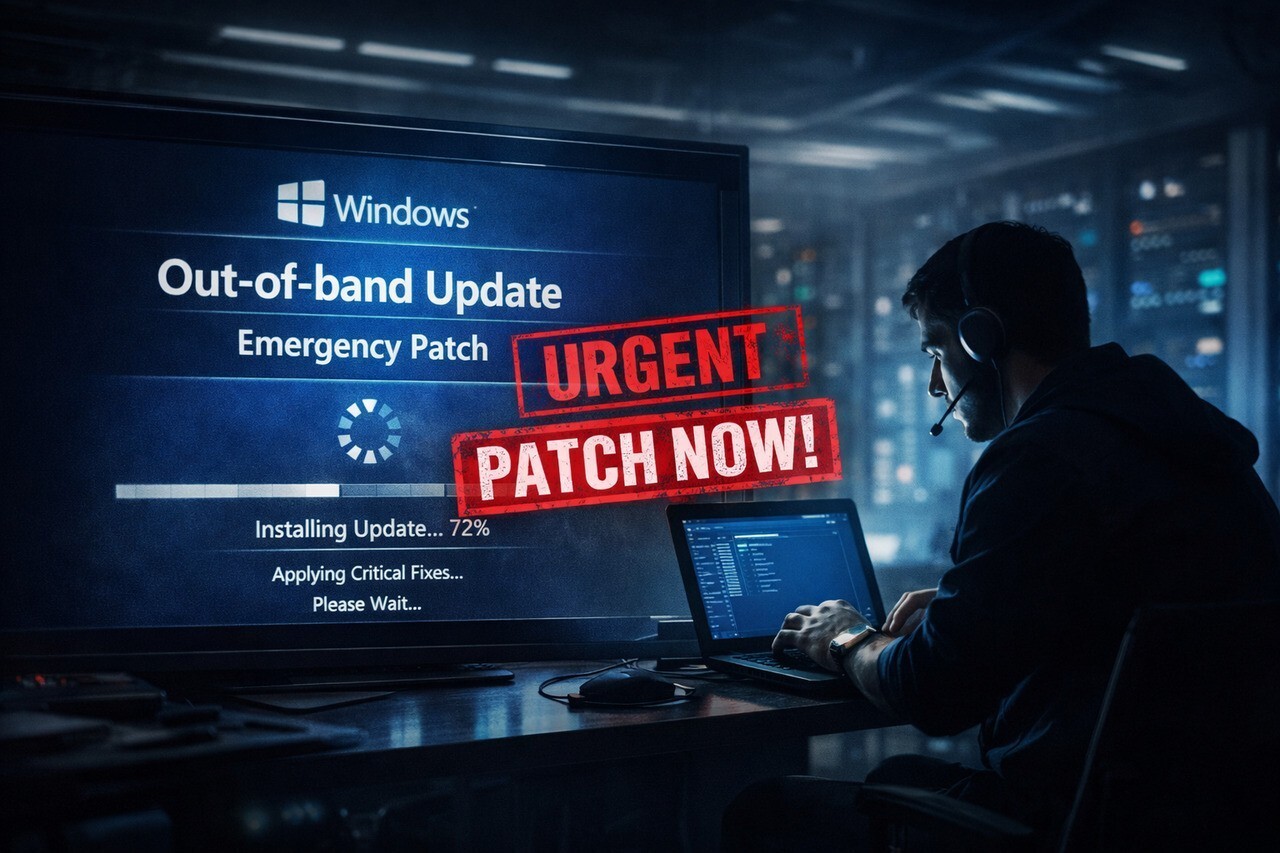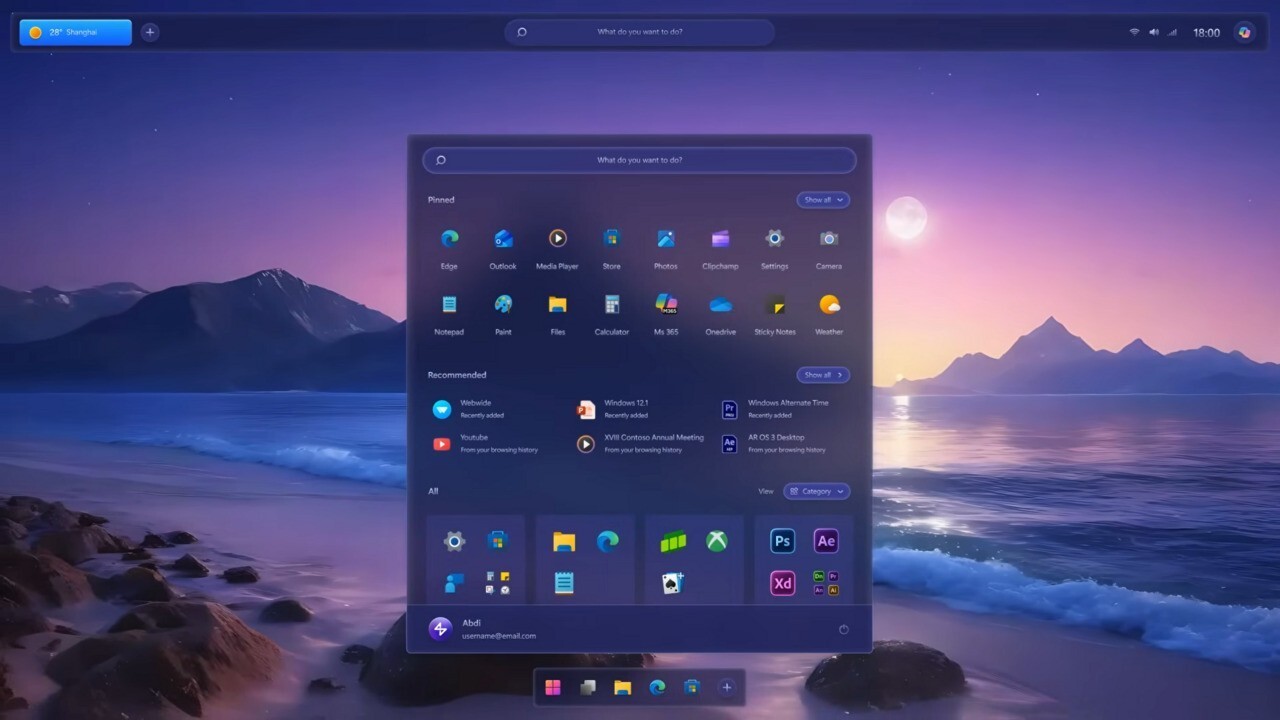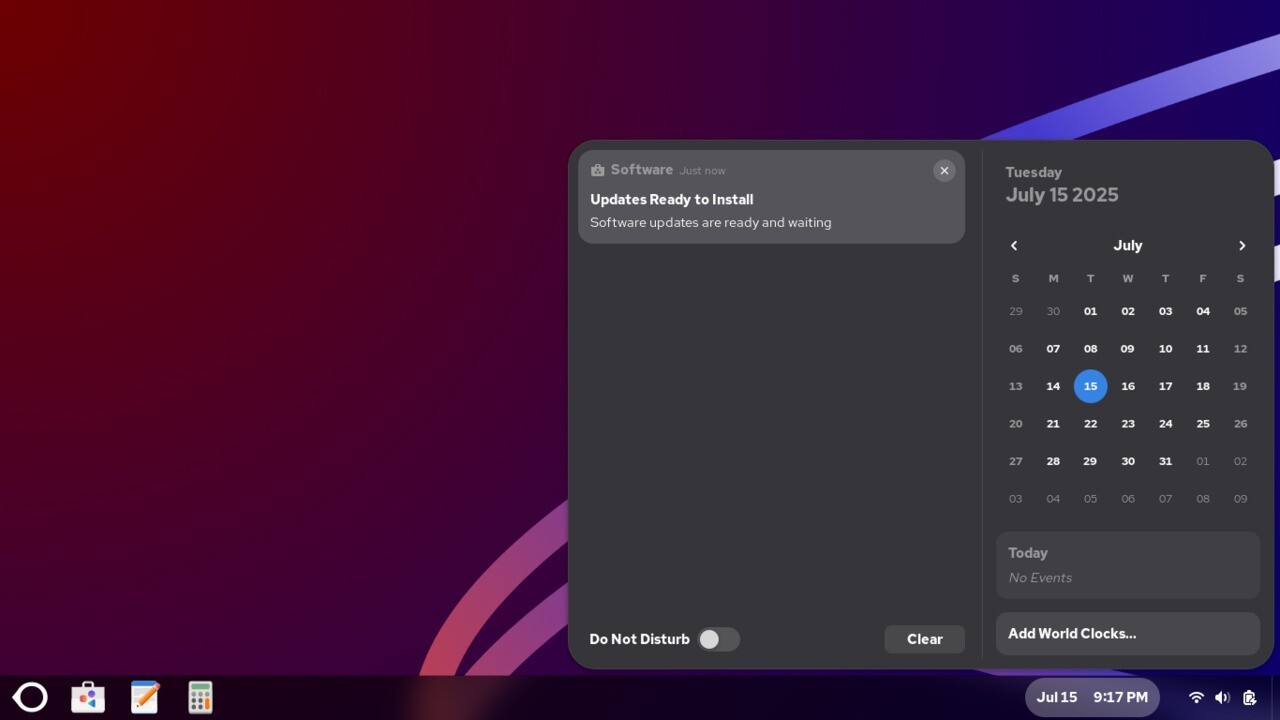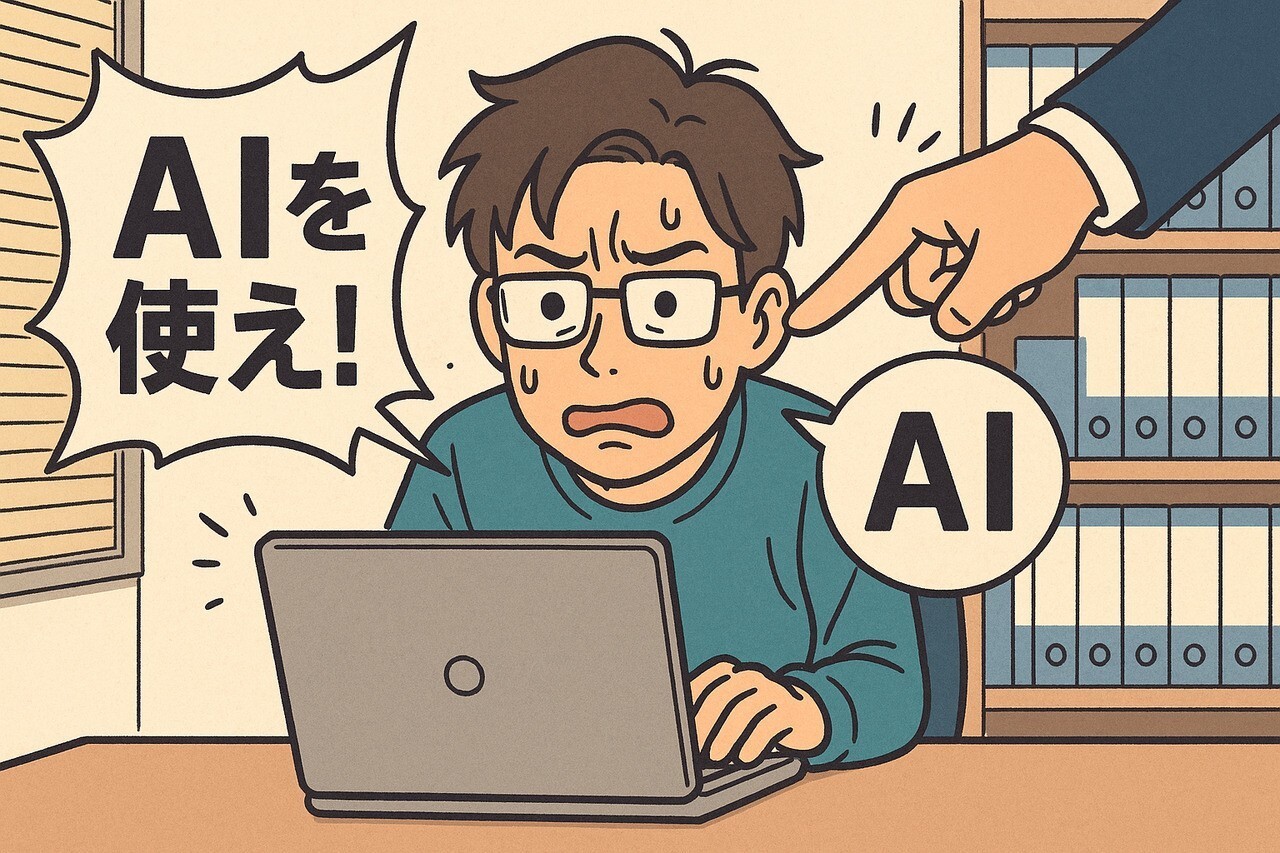
AIツールによってエンジニアの生産性が数倍になる──そんな記事を最近ますます見かけるようになっています。AIを使いこなせないエンジニアは開発者失格とみなされるほど流行し、「AIファースト」を標榜する企業の経営者は、AIを使用するよう現場に圧力をかけ続けています。しかし長い経験を持つ開発者で人気ニュースレター「Manager.dev」の創設者Anton Zaides氏は「ツールの導入ありきの戦略は、むしろ組織を疲弊させるだけだ」と警告しています。
ブログ記事「Stop forcing AI tools on your engineers」でZaides氏は、いきなり答えを出すのではなく、「もしAI導入を失敗させたいとしたら、何をするか?」という逆転の発想(インバージョン)でこの問題を考えてます。そし、以下の3つを「最悪のAI導入法」としてリストアップしています。
- AIツールの強制使用: 流行りのCursorを全員に強制、レガシーツールは禁止、APIコールはすべて「エージェント」化など、現場軽視の決定を連続する。
- 使用量によるランキングと評価制度: トークン使用量やツール使用時間を指標にするなど、「成果」ではなく「使用」を評価する愚考。
- 従来の開発手法を侮辱: 手動でログを修正するなどの行為を嘲笑する風潮が広がれば、現場の士気は地に落ちる。
これらすべてが、ツールを目的化したマネジメントの弊害だと指摘していきます。
どのようにAI導入を進めるべきか?
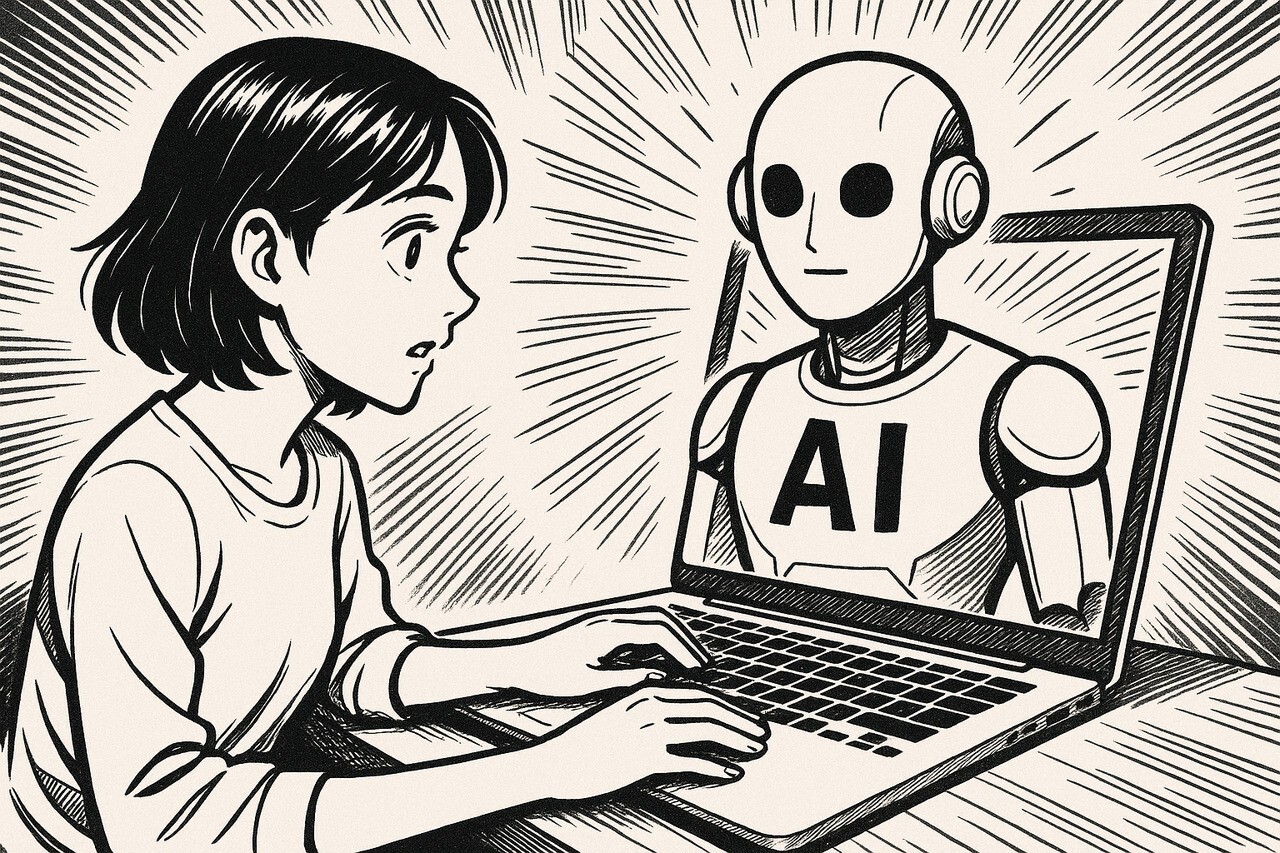
Zaides氏は、決してAI導入に反対しているわけではありません。むしろ、「正しい文脈でAIを活用すべきだ」と主張します。
まず大切なこととして、AI導入自体を目的にするのではなく、それがどのように顧客価値や業務の質向上につながるかを見極める視点が重要となります。
エンジニアがAIツールを自らの仕事にどう組み込めるかを考え、実験をできるだけの時間と余白を設けることが長期的な成長につながります。また、他社の成功事例を鵜呑みにするのではなく、社内で実際に機能した取り組みをエンジニア同士で共有することが、納得感のある導入に欠かせません。
ツールを使ったかどうかではなく、最終的な成果や改善に注目する評価体制こそが、エンジニアの意欲と創造性を引き出す鍵になると強調しています。
「AIありき」ではなく「顧客価値」を中心に
同氏は、最終目的は顧客により良いサービスを届けることにあり、ツールの多用を目的化した瞬間、本末転倒になってしまうとまとめています。
この記事はRedditでも議論されています。多くのユーザーが「選択の自由」が重要だというコメントに共感を示しており、熟練のエンジニアは「AIがむしろ邪魔になる」と主張しています。一方で「AIでレビュー作業が楽になった」「補完ツールとして非常に役立っている」など、自発的にAIを使って生産性が上がったという声も寄せられています。