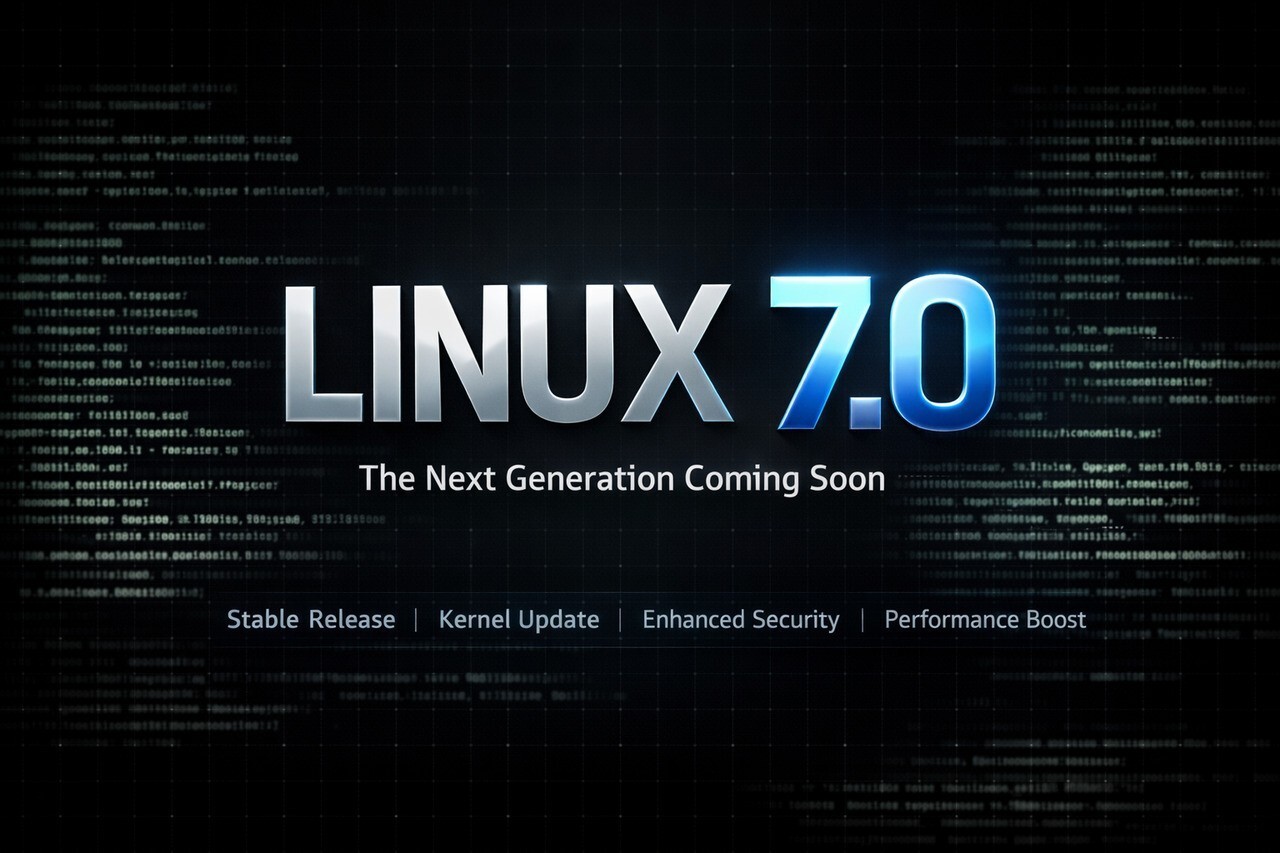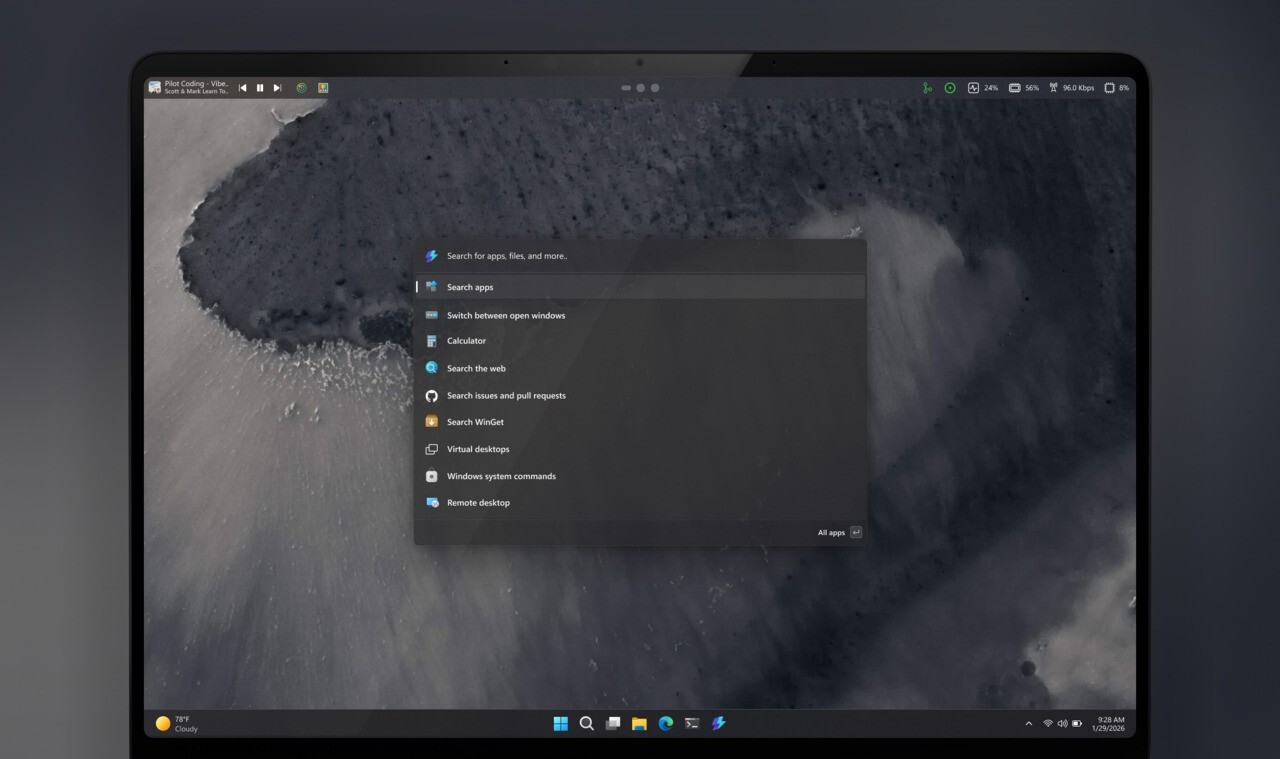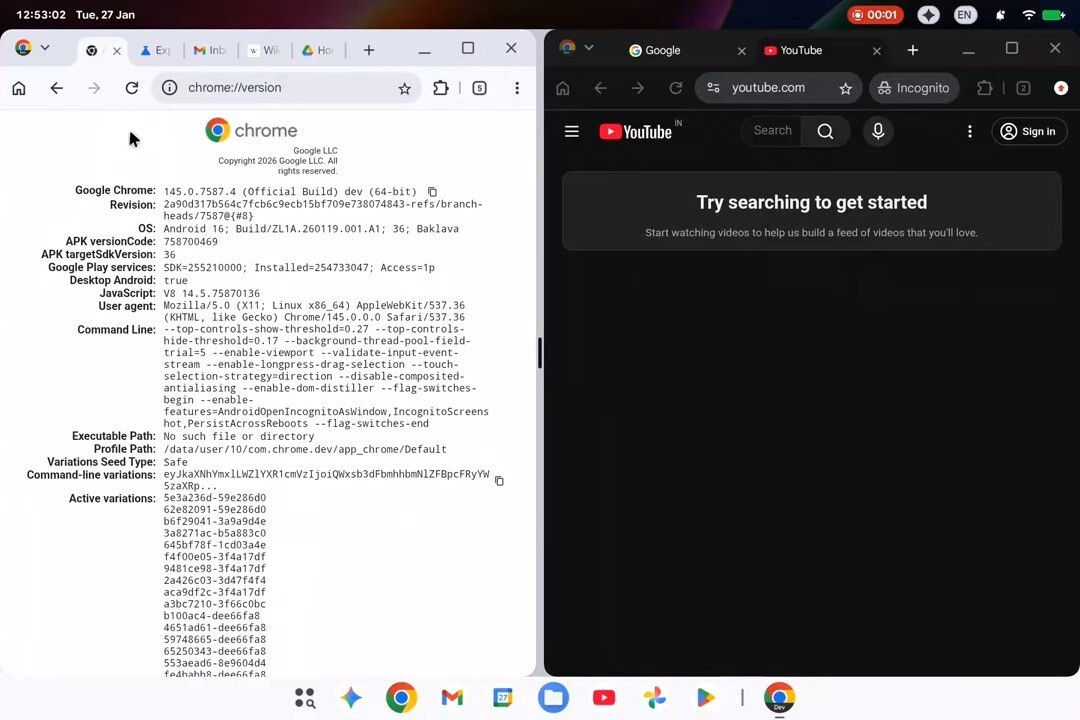AI、特に大規模言語モデル(LLM)の台頭によって、ソフトウェア開発の現場は目まぐるしく変化しています。AIによってコードの生産性が爆発的に向上しているといわれていますが、AIの普及はプラスの面ばかりではありません。開発チームは目に見えにくい代償を支払っている可能性があるのです。
開発者Jay氏はブログ記事「Yes, I will judge you for using AI...」を公開し、これまでソフトウェア開発チームがつちかってきた「信頼」の変容について考察しています。
同氏は、チームやコミュニティ内での信頼は、長期的な協働を支える重要なインフラだと主張しています。コードレビュー、設計議論、パッチのやり取り…そのすべてに「この人は理解している」「この修正は正当な理由がある」といった無形の信頼が介在しているのです。
新人とベテランのコードに対するチェックの厳しさが異なるのも、そうした信頼の段階差があるからこそですが、LLMは、経験の浅いエンジニアでも熟練者のようなコードを出力できてしまいます。これにより、コードの背後にある理解度を評価しづらくなり、レビューやコラボレーションに混乱が生じます。
しかも、LLMは「予測」によってコードを生成しており、必ずしも正しさが担保されているわけではありません。これは従来の技術的抽象化──Garbage CollectionやJITのような「正しさ前提」の技術とは一線を画しています。
この新しいタイプの「抽象化」がエンジニアリングにおけるチーム間の信頼を根本的に変化させているのです。
コードの「正しさ」ではなく「理解」が問われる時代へ

従来なら「この人がこの状況でこの設計をしたなら、ちゃんと理解しているはずだ」という推論が成り立っていました。しかしLLMを介すると、「それっぽいコード」がいとも簡単に生成されてしまい、本質的な理解が追いづらくなります。
この現象は、オープンソースのような信頼が未構築な環境で特に顕著で、パッチの精査が必要以上に複雑化し、レビュー担当者の認知的負荷が急増することになります。
Jay氏は、この問題を解決するため、今後以下のような対策が検討されるだろうと予測しています:
-
「LLM不使用宣誓」のCLA(Contributor License Agreement)導入:コードが自己の理解に基づいたものであることを保証する。
-
仮想ミーティングの強化:エンジニア同士の顔が見える関係性を構築。
-
コードの出自を示すメタデータの導入:人力 vs LLM生成を明示。
-
新人の段階的なLLM使用制限:理解力の基礎を固めるための育成措置。
ただし、これらはあくまでも現時点で実行可能なアイデアで、LLMの持つ構造的課題を解決するためには、業界全体の変化が必要だと考えているようです。
まとめ
AIはたしかに開発を加速させてくれますが、そのスピードの代償として、コードの「質」や「責任感」、そして人間関係の「信頼」が揺らいでいるのかもしれません。これからの時代は、「コードが動くかどうか」ではなく、「誰がどんな意図でそれを書いたか」という深層まで見極める力が問われていくのかもしれません。
Hacker Newsでもこの記事に関する議論が行われており、「信頼はイノベーションの速度を決める」という意見が共感を集めています。LLM導入により検証コストが増大し、信頼が築きにくくなるという懸念も多くよせられていますが、「LLMを使っても、コードの質で信頼は築ける」という立場もあり、LLMの使用自体を否定する声は少数派となっています。