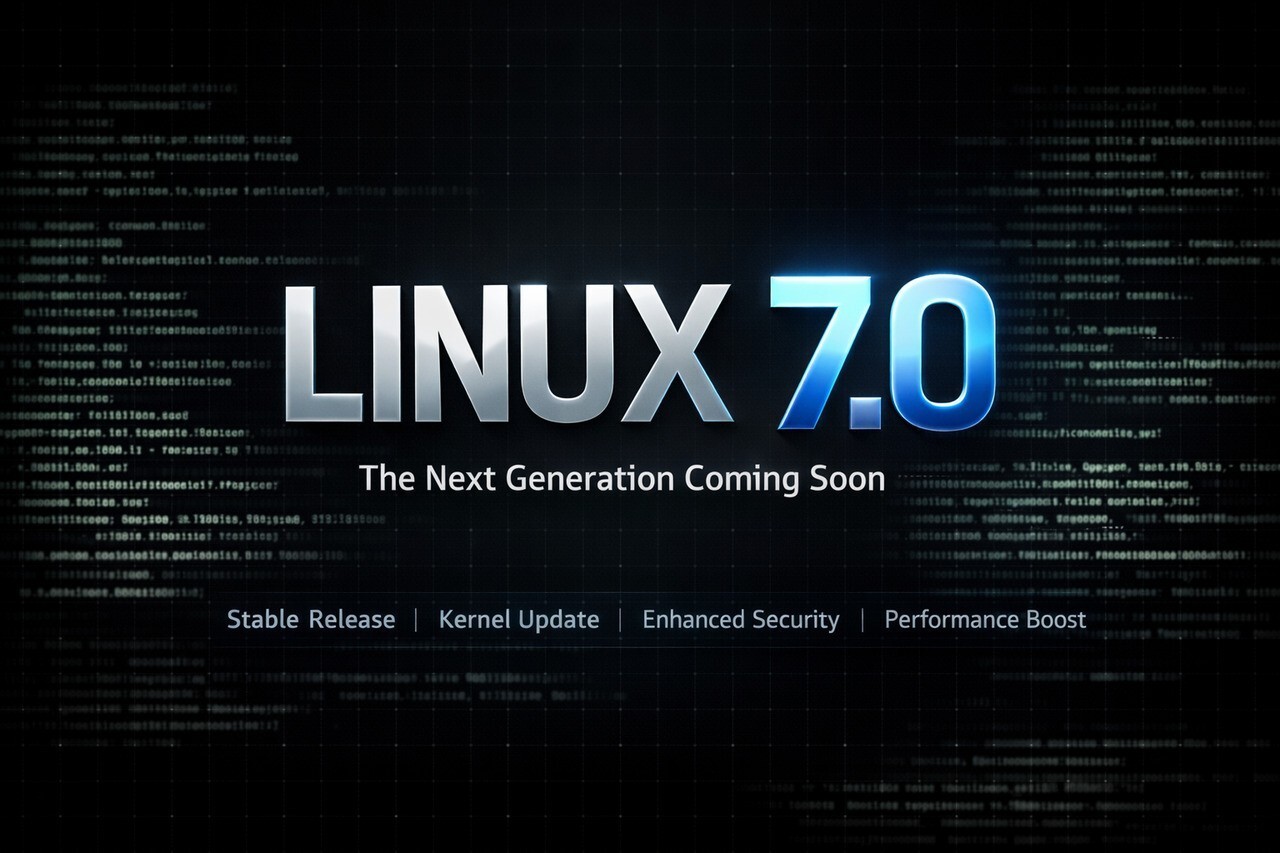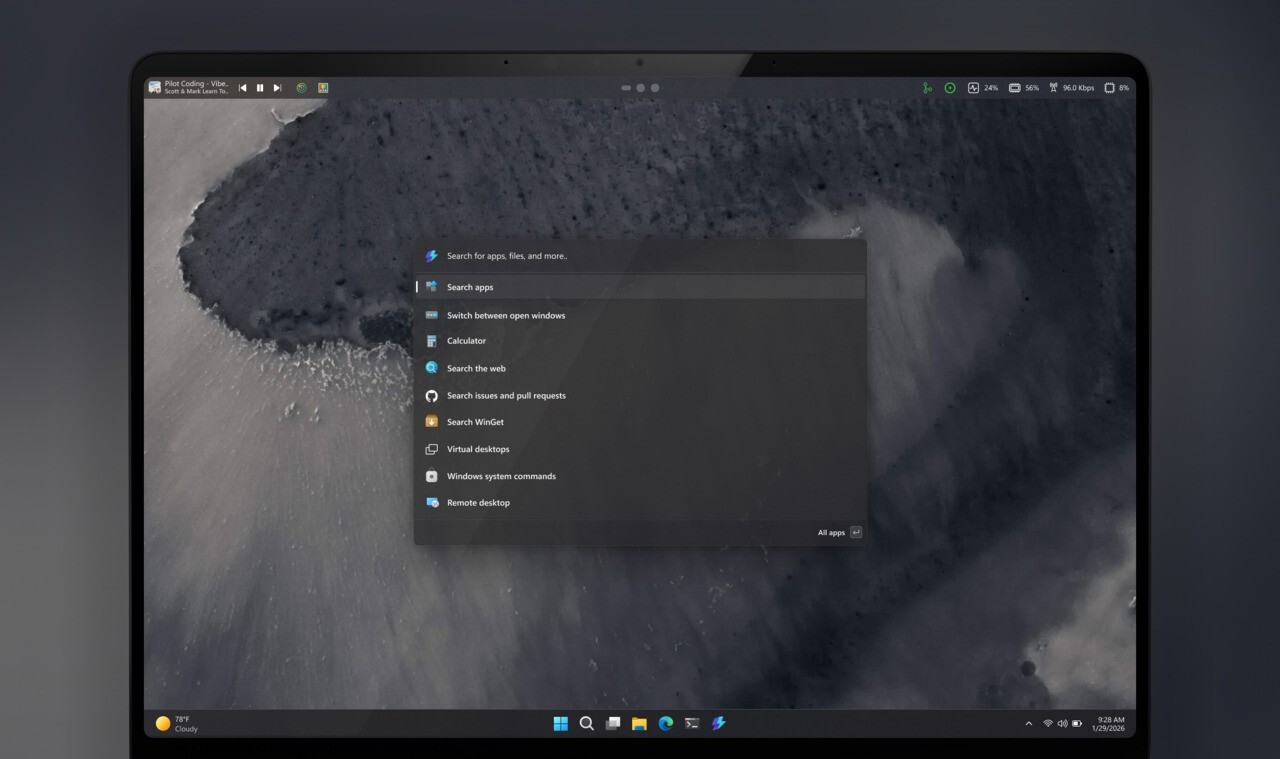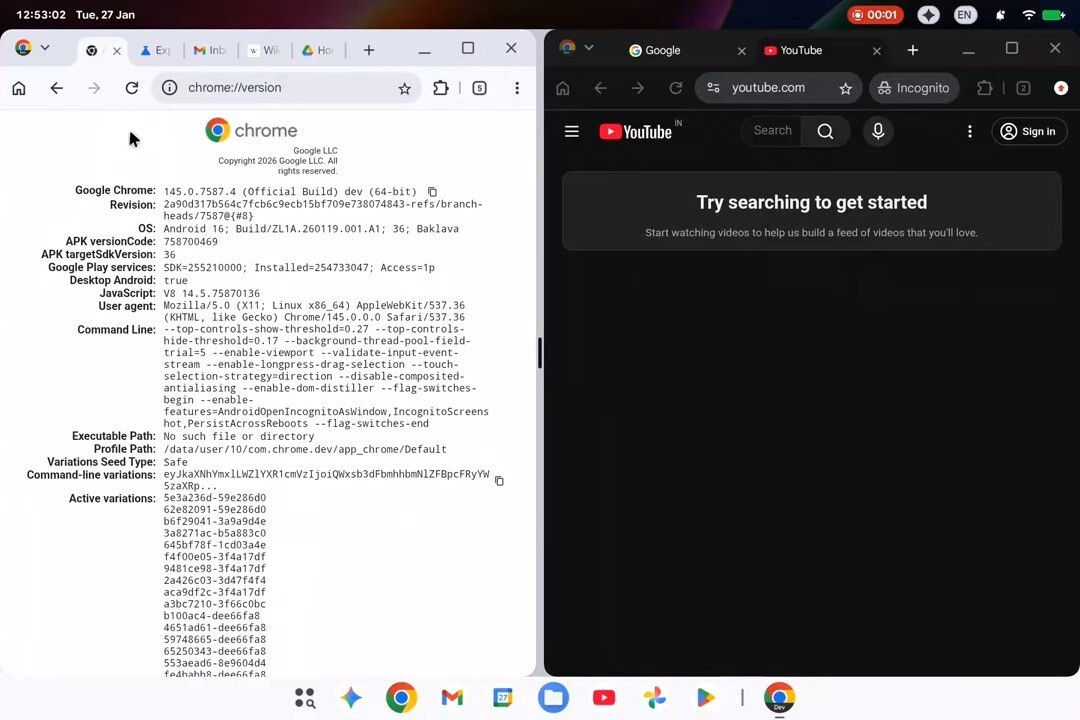2025年11月4日、Mozilla Support(SUMO)の日本語ローカライズチームが、20年以上にわたる活動に終止符を打つ決断を下しました。背景には、AI翻訳ツール「SUMO bot」の導入による翻訳品質の低下と、コミュニティとの断絶があるようです。
SUMO botは、英語版のKnowledge Base(KB)記事を自動翻訳・更新するAIツールです。しかし、日本語チームのリーダーmarsf氏は、以下の問題点を指摘しています
- 翻訳ガイドラインを無視した機械翻訳が即座に承認される
- 記事更新から72時間で自動承認されるため、新規貢献者の育成が困難に
- 300以上の記事がステージング環境を経ずに本番環境で上書きされた
- コミュニティとの事前協議や制御が一切なかった
marsf氏は「これはMozillaのミッションに対する明確な違反であり、私の翻訳をAIの学習データとして使用することを禁じる」と強く抗議しています。
他言語コミュニティの声
SUMO botの問題は多言語の翻訳者も感じているようです。
イタリア語ローカライズのリーダーMichele Rodaro氏も、SUMO botの即時介入が新規参加者の意欲を削ぐと指摘。翻訳の微妙なニュアンスや文化的配慮が失われることで、ローカライズの質が損なわれていると述べています。
一方、MozillaスタッフのKiki氏は「これはバグによる誤動作かもしれない」とし、改善の余地があることを示唆しています。対話の場を設ける提案も行いましたが、marsf氏の決意は固いようです。
Hacker Newsでは?
Hacker Newsではこのニュースに対し、「SUMO bot導入のプロセスと姿勢」に対する批判の声が寄せられています。「ボランティアの努力を無視して、品質の低い自動翻訳に置き換えた」との見方が強く、Mozillaの姿勢に失望する声が多数を締めています。
また、日本的な意思決定プロセス(根回し)を尊重すべきだったという意見がある一方で、「それ自体が非効率で問題を生む」とする反論もあり、文化論的な議論も展開されています。
さらに、「Googleからの資金でボランティアを軽視するようになった」「NGO的な“善意の押し付け”」という批判もあり、Mozillaの組織文化や意思決定の透明性も問われています。
まとめ
AI翻訳によって記事の数は増えていくかもしれません。しかし、翻訳の質が追いついていない現状では、ユーザーが本当に必要としている「わかりやすさ」や「安心感」が失われてしまう恐れがあります。これは、長年支えてきた翻訳者にとっても、読者にとっても残念な事態です。